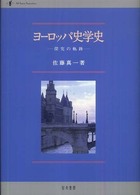 今日という日は長い歴史の積み重ねの上に存在する。しかし一口に「歴史」とはいうものの、その範囲はさまざまだ。宇宙の歴史は気が遠くなるような時間の積み重ねだが、その中で地球が生まれ、生命が誕生し、哺乳類が出現し、そこから人類が分化し、文明の歯車が回り始める。そのそれぞれに歴史があるのだ。
今日という日は長い歴史の積み重ねの上に存在する。しかし一口に「歴史」とはいうものの、その範囲はさまざまだ。宇宙の歴史は気が遠くなるような時間の積み重ねだが、その中で地球が生まれ、生命が誕生し、哺乳類が出現し、そこから人類が分化し、文明の歯車が回り始める。そのそれぞれに歴史があるのだ。
メソポタミア、エジプト、インダス、黄河その他の地域で起こった文明にも考古学的興味を大いに刺激されるが、その後ヨーロッパを中心に発展した文明の歴史を把握することは、今日私たちを取り巻く環境や思想を理解する上で、欠かすことができない。キリスト教の聖書も、この流れの中で捉えることができる記録なのである。
こうした叙述を順を追ってきちんと整理するのは想像以上に困難だ。その「歴史」がどのようなスタンスで書き残されたか知る必要もあろう。どこかの支配者が自分の栄光を後世に伝えるために都合良く史実をねじ曲げ、誇張して書かせたものには価値がない。客観的に歴史を叙述しよう、と努力した歴史家の存在と努力にこそ意義があるのだ。「誰がその“まっとうな歴史家”であり、その著作にはどのような傾向が見られ、その時代の価値観を踏まえた上でどう読み解けばよいのか」に関するコンパクトなガイドはこれまで存在しなかった。大学の哲学科で何年も研究してはじめて感じ取れるような概観を、自宅の机上でも手に入れられる──これが佐藤の『ヨーロッパ史学史』だ。
本書の構成は「古代ギリシアの歴史著述」「キリスト教の歴史観」「近代歴史学の形成」「第一次世界大戦後の歴史学」となっている。扱われている歴史家はヘロドトス、ツキディデス、ポリュビオス、ルカ、アウグスティヌス、マキャヴェッリ、フラキウスとバロニウス、マビヨン、ヴォルテール、ランケ、マイネッケ、ブロック。読み進むうちに「ヨーロッパの文化を理解する際に、今までより奥行きが深くなりそうだ」という予感が芽生えてくる。「マキャヴェッリの君主論」などというフレーズはちょっとした評論でもしばしば遭遇するが、それが実際何を意味するかきちんと把握している人はそう多くないだろう。下手に質問すると自分の無知を天下にさらすことにもなりそうで、フンフンととりあえず受け流してはいないだろうか? それを解決する糸口が見つかりそうだ。
何事においても「大きな流れ」を俯瞰することが大切だ。佐藤は西洋の歴史観と歴史学の大きな流れを示してくれる。久しぶりに噛みごたえがあるドイツパンのような本に出会えたことが嬉しい。何年もかけてまとめられた力作である。その内容は緻密だが、表現は平易だ。誰でも読める。最後に著者自身の言葉を紹介しておこう。
「歴史はともすると無味乾燥な暗記物と考えられがちである。しかし、歴史家たちとその著作を彼らの生きた時代の中で理解することによって、歴史の豊かさを知ることができる。また、歴史の探究は現代を生きることと深く関連している。このことを伝えたいと考えた(p.304)」(知泉書館)