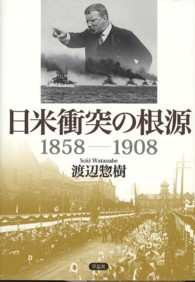 二年前にもこのブログで同じ著者による『日本開国』を紹介したが、その後も継続して行われた地道なリサーチの成果がふんだんに盛り込まれた力作が上梓された。本書には1858年から1908年に至る時代──日本における明治時代──のアメリカ国内の発展と日米関係の推移が克明に語られている。多くの資料から得た情報を適切な順序で著述していくことによって、読者はあたかも歴史小説を読んでいるかのような気持ちにさせられる。全体の流れを自然に俯瞰できる点は、前著に比較して格段の利点と言えよう。
二年前にもこのブログで同じ著者による『日本開国』を紹介したが、その後も継続して行われた地道なリサーチの成果がふんだんに盛り込まれた力作が上梓された。本書には1858年から1908年に至る時代──日本における明治時代──のアメリカ国内の発展と日米関係の推移が克明に語られている。多くの資料から得た情報を適切な順序で著述していくことによって、読者はあたかも歴史小説を読んでいるかのような気持ちにさせられる。全体の流れを自然に俯瞰できる点は、前著に比較して格段の利点と言えよう。
ヨーロッパからアメリカ大陸に渡ってきた白人にとって国家の起点は東海岸だが、その後カリフォルニアで金鉱が見つかったことなどにも影響されて西海岸への興味が格段に高まった。それは大陸横断鉄道の実現にもつながり、海を越え、遠くアジアへ至るルートが積極的に開発されていったのだ。これは貿易のみならず軍事にとっても大きな変化をもたらした。ハワイが他国に支配される前に併合しようとアメリカが試みたのも、貿易船のための石炭補給基地としてばかりでなく、アジア地区における軍事戦略を有利に展開するためだし、フィリピンもさまざまな観点から重要な拠点のひとつとして捉えられていた。
明治政府を設立して開国に踏み切った直後の日本の外交は、まだまだ稚拙なものだった。アメリカはもとよりヨーロッパの強豪が軍事力によって日本を属国として支配しようとしたならば、それはおそらく可能だっただろう。しかし日本を訪れた外国人たちが日本から受けた印象、そして日本人が使節団として諸外国を訪問した際に与えた印象──毅然とした誇り高き礼節、旺盛な学習意欲と優れた理解力、そしてそれらをみるみるうちに我がものとしていく柔軟な吸収力──は非白人民族の中で特にきわだった存在として尊重されたようだ。そのあたりは著者渡辺が翻訳した『日本1852』に詳しいが、とりわけアメリカには「日本を自立させるための援助を惜しまない」という気運が生じたようだ。アジアは欧米の列国の経済発展にとって重要な地域であるからこそ、お互い牽制しあっていた──特定の国が日本を勝手に支配するようなことは政治力学上不可能だった──という国際政治のバランスも、日本にとって幸いだったに違いない。
本書を読んでいて思うのは「国益とは何か」ということだ。さまざまな条約が締結される裏には当事者たちのさまざまな権益や思惑が渦巻いている。意図的に相手をあざむこうとする場合もあるだろうし、そうした駆け引きが最終的には武力衝突へと発展する場合もあろう。開国間もない日本は、地域のクラブに属していたサッカー少年や野球少年が突然プロリーグに放り込まれたようなものだったに違いない。後に引くわけにはいかないものの、よきアドバイザーなしでは判断を誤り、奸計に嵌ってしまう。そんな中、アメリカは日本の見方をしてくれたのだ。そして、日本は短期間のうちに多くを学び、軍事力も充実させていった。今日の日本の「アメリカがくしゃみをすると日本が風邪をひく」とまで言われる関係がこの当時に根ざしたものかは不明だが、本書を読んだ限りでは、アメリカは日本にとってとりあえず「いいヤツ」だったように思われる。(草思社)