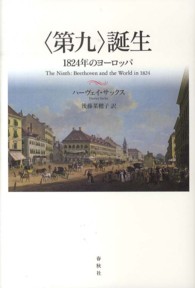 「第九」とはもちろんベートーヴェンの作曲した交響曲第9番のことである。聴覚を失った最晩年のベートーヴェンが創作した大規模な交響曲だ。最終楽章で混声合唱による「歓喜の歌」が高らかに歌われるこの作品が日本における年末コンサートのプログラムとして定着し、多くの人に愛されていることは、御承知の通りである。
「第九」とはもちろんベートーヴェンの作曲した交響曲第9番のことである。聴覚を失った最晩年のベートーヴェンが創作した大規模な交響曲だ。最終楽章で混声合唱による「歓喜の歌」が高らかに歌われるこの作品が日本における年末コンサートのプログラムとして定着し、多くの人に愛されていることは、御承知の通りである。
有名だが、決してわかりやすい作品ではない。鑑賞したときに感じる圧倒的なエネルギーはともかく、作品の細部に託されているさまざまな意図と目的を解き明かそうとする作業は、一筋縄ではいかない難行となる。しかしこうした「作品を哲学する」ような研究も、また楽しいものだ。ベートーヴェンファンならなおさらだろう。ベートーヴェンに関する諸々は研究対象としても充分な手ごたえがある上に、未だに研究しつくされたとはいえない、奥の深い世界なのだ。
ベートーヴェンに関する書籍は枚挙にいとまなく、テーマを第九に特定した書籍も、かなりの数にのぼる。アジア地区で最大の音楽図書館である国立音楽大学の図書館で調査してみたところ、タイトルに「ベートーヴェン」が含まれる和書をキーワード検索すると379冊、「第九」のキーワードでは28冊がヒットした。加えて「Beethoven」がタイトルに含まれる洋書は約千冊。大変な数である。本書もその中の一冊だ。
著者のサックスはフィラデルフィアのカーティス音楽院で教鞭も執っているが、自身は本書冒頭の「はじめに」の中で「私自身は音楽学者ではないことをここで告白しておかなければならない」と述べている。「きちんと学んで学位を取得した人々のように学者を名乗る資格はない」というのだ。しかしフルタイムの作家としての活動や指揮者としての経験、そして旺盛な好奇心を満たすべくさまざまなことにチャレンジし、吸収し、自分の知見を充実させた末の今、著者はより広い視点から見たベートーヴェン像をわれわれに提示してくれる。
本書ではベートーヴェンとその時代の文化を、難解と言われる「第九」を軸にしながら観察するわけだが、登場人物は音楽関係者のみならず、作家や画家、そして政治家など多岐にわたっている。さまざまな文化や歴史が激動する「渦中のヨーロッパ」、そしてそこに仁王立ちしていたベートーヴェンとその作風が、さまざまな切り口から解析される。
本書193ページ以降で展開される第九交響曲の音楽描写は、サックスが指揮者としての側面を縦横に発揮した、興味深い内容となっている。CDとミニチュアスコアを用意して、この解説を読みながら音楽の進行をたどっていくと、今までは何となくやり過ごしていた多くのアイデアや意味づけはもちろんのこと、ベートーヴェンの驚異的な作曲手腕にも気づかされるだろう。あくまでも著者の主観であり、ベートーヴェン自身がそう思って作ったかどうかは定かではないにせよ、芸術の域にまで完成された音楽作品がいかに繊細かつ堅牢に構築されているかを思い知らされることになろう。また、これを参考にしながら異なる指揮者とオーケストラの演奏を聞き比べてみれば、いままで漠然と感じていた違いが、より具体的かつ鮮明に把握できるに違いない。
「純粋に音楽が好き!」という面々には、少々くどい内容かも知れない。しかしベートーヴェンの音楽に盛り込まれているくどさとしつこさは、もともと並大抵のレベルではないのである。作家としてそれを語るためには、おそらく相当の覚悟が必要だったことだろう。
音楽の内には音楽以外のさまざまな営みから生じるエネルギーが渦巻いている。その渦中にいて、流されずに自分の理想に向かって着実に歩んでいった偉人たちの精神力と行動力には、改めて驚嘆させられる。19世紀前半、いわゆる「ナポレオン後」というヨーロッパ史の中でも興味深い時代を、音楽も含めた文化面全般から俯瞰するにはうってつけの書籍ではないだろうか。 (春秋社)