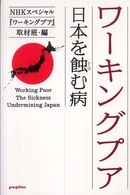
 ワーキングプア。悲痛な響きだ。最近使われるようになった言葉だが、目いっぱい働いても生活保護の水準にも届かないような収入しか得られず、人生の将来像を描くことがまったくできない人々のことだ。正社員や専任講師のように給与が保証され、まがりなりにも銀行から借金ができる人には実感がわかないかも知れないが、今は安定している人でもちょっとした行き違いから同じ境遇に陥る危険があるところが恐ろしい。一寸先は闇なのだ。
ワーキングプア。悲痛な響きだ。最近使われるようになった言葉だが、目いっぱい働いても生活保護の水準にも届かないような収入しか得られず、人生の将来像を描くことがまったくできない人々のことだ。正社員や専任講師のように給与が保証され、まがりなりにも銀行から借金ができる人には実感がわかないかも知れないが、今は安定している人でもちょっとした行き違いから同じ境遇に陥る危険があるところが恐ろしい。一寸先は闇なのだ。
商店街を歩いていて、どう見ても成り立ちそうにないお店にめぐり会ったことがあるだろう。「ひょっとすると地主さんで、本業はアパート経営でもやっているのかも知れないな」などと好意的に解釈してはいなかっただろうか? 自転車に空き缶を山積みにして運んでいる人を見たこともあるだろう。「どういう経路をたどろうとも、いずれリサイクルされる缶だから良いものの、捨てられていた空き缶の所有権は本来誰にあるのだろう」などとは考えなかっただろうか?
こうしたシーンは、社会的な構造欠陥から必然的に生じてしまったワーキングプアと直結した状況なのだ。今、お金がない。とにかく何かをしなければ、死を待つしかない。しかし身を粉にして働いても賃金は安い。これでは経済的な余剰が出るはずもなく、将来の展望も閉ざされたまま微動だにしない。
怠けているのではない。働きたい、という意志はあるし、チャンスがあればそれを可能な限り利用し、限界まで追い詰められながらも必死に働いているのだ。それでも何も解決しないし、できない。
実生活には「貧富の差」などと軽々しく口にできない厳しさがある。こうした事態は何も特殊ではなく、私たちのすぐ身近にころがっているという、戦慄すべき状況なのだ。NHKスペシャル取材班の『ワーキングプア──日本を蝕む病』は、そうした状況を痛いほどの鮮度で提示してくれる。
一方、水月昭道の『高学歴ワーキングプア──「フリーター生産工場」としての大学院』には、「就職にあぶれないように」という保険の意味もこめて高学歴を獲得しても、それが何の役にも立たないばかりか、かえって就労の邪魔になることさえある、という現実が書かれている。しかし著者の水月は「自身も同じような崖っぷちに立たされている」という危機感から、そうした状況をどうとらえ、理解したら将来への光を少しでも見出せるようになるか、という提案をしてくれる。それがたとえ机上の空論だとしても、少しだけほっとできるのが救いだ。しかし本書を通じ、博士号まで持ちながらも、ひとたびワーキングプアのスパイラルに巻き込まれると、そこから脱却するのが容易ではないことがよくわかる。
暗い世の中になってしまったものだ。閉塞感。やるせなさ。政治とは何なのか。誰のための政治なのか。「景気は上向き」などとは、どこの誰が言い出したことなのだろう…。(光文社新書)