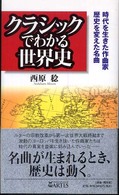本書のタイトルは「クラシック音楽を利用して世界史を勉強しよう」と読めるが、そうではない。「世界史と対応させることによってクラシック音楽をより深く味わうための本」なのだ。音楽の歴史を俯瞰することは確かにクラシック音楽の理解に役立つが、いかんせん、楽しく読める音楽史の本に出会ったことがない。楽しく学べない知識はなかなか身についてくれないものだがこの本はそうではなく、「もっと知りたい!」と読む者をわくわくさせてくれる。
音楽に限らずさまざまな名作を鑑賞するときは、その作品を創作した作家の心情に思いを馳せるだろう。こと音楽では「ああ、このメロディがこれほど悲痛に響く裏には、そんなに悲しい出来事があったのか」と涙し、共感を深めるわけだ。
しかし創作活動の原動力となるのは作家の個人的・内面的な欲求だけではなく、社会的な事件や背景が大きなきっかけとなることが少なくない。バッハはなぜあのような音楽を書いたのか? 音楽家モーツァルトにフリーメイソンはどのような影響を与えたのか? そしてベートーヴェンやシューベルトの音楽をフランス革命、ナポレオンとその後メッテルニヒによる弾圧・検閲の世相を考慮せず理解することは不可能だ。今日“芸術”として鑑賞される作品の中で少なからぬものは個人的心情の訴えにとどまらず、社会体勢への共感や協力、あるいは果敢な挑戦として創作されたのだ。
貴族や宮廷の中で楽しまれていた音楽が庶民の生活に浸透していった状況も、音楽史としてとらえるだけでは不十分だ。一般市民が台頭していく過程は社会全般の変化として理解すべきもので、音楽はそのごく一部に過ぎない。
世界史(ヨーロッパ史)と音楽史をつきあわせることによって、「そうだったのか!」と納得できることは多い。作曲家とは自分の好きなことに没頭しているだけの“趣味の人”ではなく、実はどれほど雄弁な英雄だったかは、それぞれの時代の社会背景を知って初めて納得できるのだ。一般的な歴史の知識は音楽をより深く理解するために欠かせないどころか、音楽をもっと楽しむためのカンフル剤となろう。
今まで音楽史の本はたくさんあったし、世界史の本もそれ以上に出版されてきた。しかしそれを同列につむいだ本はあっただろうか。音楽史を「ルターの宗教改革から第一次世界大戦終結まで」という波瀾万丈なヨーロッパ史と合体させたこの本は、今まで不足していたユニークな視点を音楽ファンにもたらしてくれるに違いない。(アルテスパブリッシング)