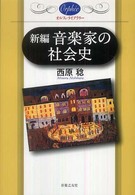 数十年前に出版された『音楽家の社会史』がこのたび「新編」として再版されることになった。大歓迎だ。歴史の本にありがちな古色蒼然とした内容とは一線を画し、現代の世相につながる接点がたくさん含まれている。今回あらためて読みなおしても、とても新鮮に感じられた。
数十年前に出版された『音楽家の社会史』がこのたび「新編」として再版されることになった。大歓迎だ。歴史の本にありがちな古色蒼然とした内容とは一線を画し、現代の世相につながる接点がたくさん含まれている。今回あらためて読みなおしても、とても新鮮に感じられた。
本書では18世紀から19世紀にかけてヨーロッパで活躍していた音楽家たちの実生活が紹介されている。具体的にはモーツァルトからシューマン、ショパン、リストあたりまでの世相と思えばよいだろう。作曲家にとっての著作権や作曲料に関する実情、あるいは演奏家として生計を立てる際に直面せざるを得ない数々の経済的なハードルなどに関する話題が、生き生きと描かれている。
その昔、音楽家は王侯貴族の庇護のもとで活動していた。おかかえ音楽家として雇用者の満足のために作曲し、演奏することによって生活が保障されたのだ。報酬は現金とは限らず、食料品などの現物支給も一般的だった。音楽好きな領主に恵まれれば優れた楽士たちはそれなりの寵愛を受け、人々からの尊敬を得ることもできた。しかし、世間一般の常識では音楽家の地位など料理人のそれと同等だった。モーツァルトもベートーヴェンも演奏家として招待された邸宅でそのような待遇を受け、プライドをいたく傷つけられた経験を持っている。
コンサートの形態にしても、当時と今日のものとでは大きな差があった。詳細は本書にくわしく述べられているので割愛するが「いつの世でも音楽家の苦労はつきないなあ」というのが実感だ。演奏者の収入源は聴衆が支払う入場料だが、ここからさまざまな経費、とりわけ照明にかかる費用(シャンデリアにともす蝋燭代──大きなホールではこれがかなりの額となってデビューしたての演奏者を困惑させた)は、演奏活動の根幹を揺るがしかねないほど大きな負担になったという。それやこれやで収入よりも支出の方が上まわってしまうことも今日同様、日常茶飯事だったようだ。
音楽家と批評家との問題もとりあげられている。音楽ジャーナリズムの台頭により、社会的に影響力をもつ評論家が幅を利かすようになった。見当外れで身勝手な評論を発表する評論家とそれに憤る演奏家という構図は、今に始まったことではなかったのだ(これに関してはスロニムスキーの『名曲悪口事典』もおもしろい)。
当時の音楽家の収入額などが随所に具体的に書かれているのも興味深い。ヨーロッパの通貨にはさまざまな単位があり、その換算法も10進法とは限らない。何らかの基準を定めて今日の金銭感覚と対比可能なレベルに整理するのは、現実問題として不可能に近いだろう。それでも本書を読んでいて「これぐらいかも知れないなあ」という感覚を得られるのは、なかなか貴重である。
音楽だけでは御殿が建ちそうにないことは、今も昔も変わらないようだ。それでも音楽は継承される。今日までの音楽家たちの労苦と努力とに敬意を表したい。(音楽之友社)