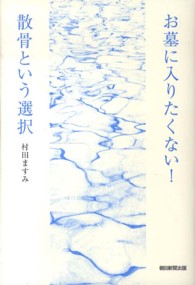 人生には、年を重ねてこそ初めてわかることがある。心意気はまだ若くても、体力の衰えを実感するようになり、心配事が増えてくる。二十代の頃には想像できなかった現実にいやおうなく直面させられるのだ。たとえば、なってみないと老眼の不便さはわからない。食事中、自分が食べているものに焦点が合わないのは、実にせつない。また「体力が落ちてくる」とはどういうことかにも思い知らせられる。駅の階段を駆け登るのも息が切れるし、ましてや1段抜かしで駆け降りて電車に飛び乗る、など今ではとてもできない。年金生活への漠然とした不安も無視できないし、認知症になったらどうしよう、という心配もある。
人生には、年を重ねてこそ初めてわかることがある。心意気はまだ若くても、体力の衰えを実感するようになり、心配事が増えてくる。二十代の頃には想像できなかった現実にいやおうなく直面させられるのだ。たとえば、なってみないと老眼の不便さはわからない。食事中、自分が食べているものに焦点が合わないのは、実にせつない。また「体力が落ちてくる」とはどういうことかにも思い知らせられる。駅の階段を駆け登るのも息が切れるし、ましてや1段抜かしで駆け降りて電車に飛び乗る、など今ではとてもできない。年金生活への漠然とした不安も無視できないし、認知症になったらどうしよう、という心配もある。
そんな心配のひとつに、お墓の問題がある。
一昔前までは「死んだらその家の墓に入る」という世間一般の流れがあった。子は親の墓に入り、よほどの事がなければ嫁も一緒に入れられる。「先祖代々の墓」であり、折々に営まれる法事は普段会うこともない親戚一同が集まる場となる。しかし今そうした常識は通用しない、というのだ。
その原因にはいろいろあろう。背景には若い世代の考え方の変化ももちろんのこと、少子化、核家族化をはじめとしたさまざまな事象が存在する。「墓を維持する」ということが当然の義務ではなくなりつつあるのが、21世紀の風潮のように見受けられる。
最近は社会的な知名度の高かった人でも葬儀は家族のみによる密葬として営まれることが多く、大きな葬儀場で大々的に行われるのはよほどの人物か芸能人だけになってしまったような感もある。それどころか近年は葬儀そのものをスキップし、遺体を病院から直接火葬場に運ぶよう葬儀社に依頼する家族も急増しているそうだ。
熟年離婚が増加する中、墓の中まで夫と一緒にいたくない、という妻も多いと聞く。「自分は自分の墓に入る。ひとりでも構わない」というわけだ。しかし、墓を買って入ったは良いが、子供がいなければその後はどうなるのか? 実は「墓を買う」とは言うものの、これは「墓」という不動産を手に入れたのではなく、「墓を使用する権利」を取得しただけなのだ。対価が支払われなくなれば、その権利もいつかは消滅する。
そんな中で「墓はいらない。自分が死んだ後は散骨して欲しい」と希望する人が増えてきたそうだ。しかしまだ一般的ではなく、どうしたら良いのかわからず戸惑っている人も少なくないに違いない。まだ元気なのに、死んだ時のことを言い出すのは家族の手前はばかられる、という人もいるだろう。
もっとも、「自分が死に至るまでの最後の日々」と「自分が死を迎えた時とその手当」のことは、まだ元気な時にこそ平常心で家族と話し合っておくべきだと思う。「誰かに決めてもらう」のではなく「自分で決める」ことが大切だからだ。衰弱して自分の意志を伝える力を失った人を前に、こうしたことを決めざるを得ない家族のストレスを思いやるだけの度量が欲しい。
著者の村田ますみは、遺言によって散骨を希望した実母の葬儀経験を通じていろいろ感ずるところあり、最終的には自ら海洋散骨をサポートする会社を設立するに至ったという。その時に感じたこと、調べたこと、わかったこと、留意すべき事などが、細やかな女性の思いやりとともにわかりやすくまとめられている。人生の終え方のひとつの選択肢として、一読しておくと良いだろう。誰もが例外なく一度はたどらなければならない道だからだ。 (朝日新聞出版)